1. AIに仕事を奪われるの?という不安から始めよう
「AIって、私たちの仕事を奪うの?」
「子どもたちは、ロボットと一緒に生きていく時代になるの?」
そんな疑問や不安を持っている方も多いのではないでしょうか。
2025年に開催された大阪万博国際大会では、世界のテクノロジーリーダーたちが集まり、「AI」「Web3」「メタバース」について最新の見解を語りました。
今回は、Yu Yuan(ユ・ユアン)氏の登壇をまとめます。
2. 登壇者紹介:ユ・ユアン氏とは?
- Yu Yuan(ユ・ユアン)氏
- 2023年 IEEE Standards Association(国際標準化機構)の主席
- Metaverse Acceleration and Sustainability Association(MASA)のCEO
世界中のテクノロジー政策や産業のルールづくりに関わり、「人とAIの共存」を真剣に考えているキーパーソンの一人です。
彼の話は一見難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はとても身近で、子どもでも共感できるメッセージが詰まっていました。
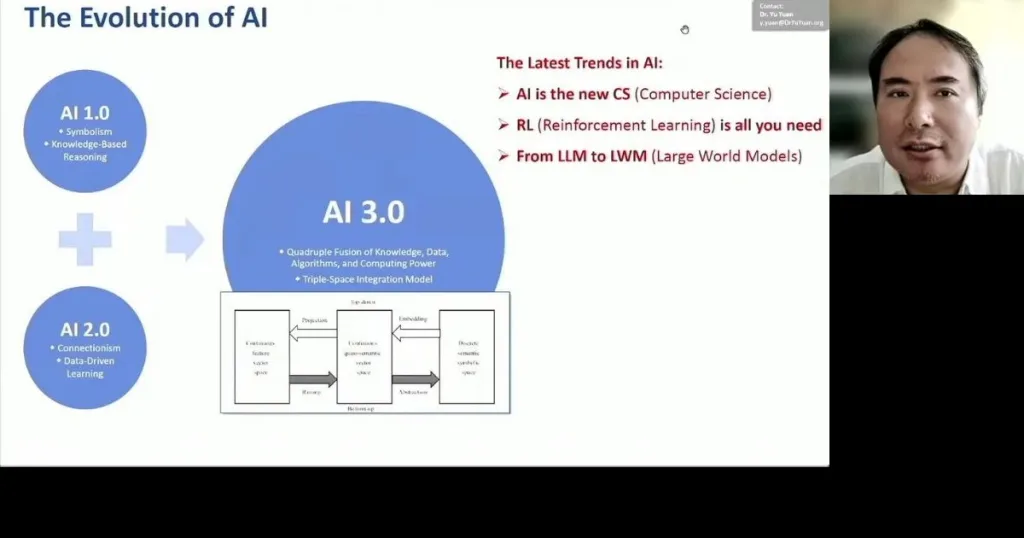
3. 「難しい話」をやさしく伝える3つの視点
視点①:AIと人は、敵ではなく“相棒”になる
Yu氏は、「AIが人を超える」と恐れるのではなく、「AIと人が協力する未来」を描いています。
AIには、人間より得意なことがたくさんあります。
- 大量の情報を瞬時に処理する
- データからパターンを見つける
- 休まず正確に動ける
でも、人間にしかできないこともあります。
- 思いやりや共感を持つ
- 新しいアイデアを生み出す
- 他人と協力して成長する
AIと人が「できること」を分担し、お互いの良さを活かす。
それが、これからの未来の働き方です。
たとえば──
お手伝いロボットがご飯をつくってくれる未来が来ても、
「ありがとう」と伝える相手がいないのは、少し寂しくありませんか?
視点②:仕事がなくなる?いいえ、「仕事の意味」が変わる
「AIが出てきたら、仕事がなくなる」
そんな話もよく聞きます。
でもYu氏は、「人間の仕事が“ゼロ”になるわけではない」と語ります。
むしろ、AIが単純作業を代わりにやってくれることで、
人間は「考える・創る・つながる」という、より創造的な仕事に集中できるようになるのです。
宿題をAIが代わりにやってくれたら、
子どもはもっと絵を描いたり、ゲームをつくったりできるかもしれない。
それが“未来の働き方”なんです。
視点③:メタバースは「遊び場」から「学びと仕事の場」へ
「メタバース」と聞くと、ゲームのような空間を想像する人が多いかもしれません。
でもYu氏は、「メタバースは未来の学校や会社にもなりうる場所」だと言います。
- 世界中の人が同じ空間で会議する
- 子どもたちが、バーチャル空間で歴史を体験する
- アーティストが作品を展示し、世界中からフィードバックを受ける
こうした空間は、遊びだけでなく「学び」や「経済活動」の場所になりつつあります。
➡ メタバースの最新活用事例は、以下の国際大会レポートでも紹介しています。
👉 国際大会レポートを読む
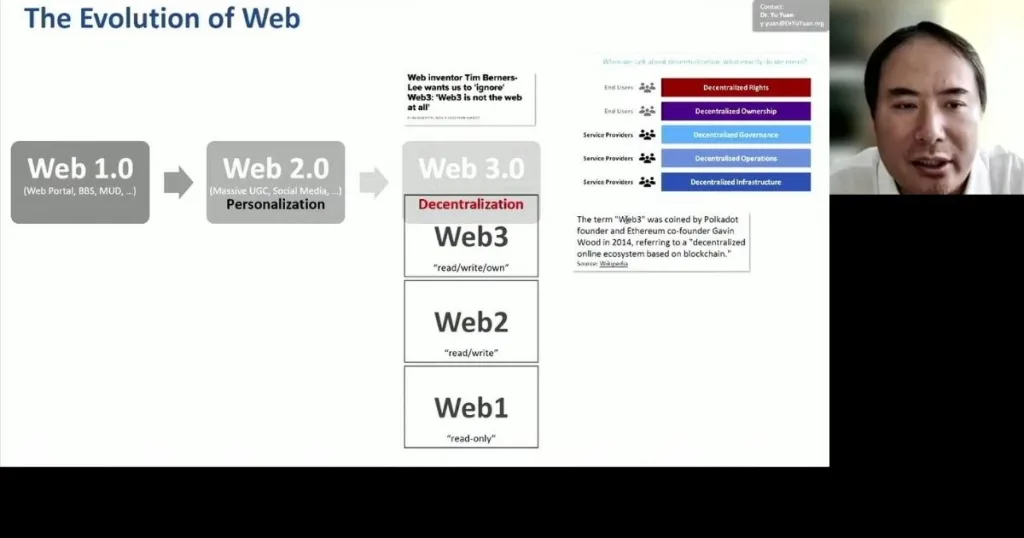
4. テクノロジーの暴走を止めるのは、人間の想像力
Yu氏は、テクノロジーの加速についても警鐘を鳴らします。
「AIは、これから年に10倍のスピードで進化する」との予測も。
このままだと、一部の巨大企業だけが力を持ち、人間の働く場が失われてしまう──
そんな懸念も現実味を帯びてきています。
でも彼はこう言います。
「人間が主役であり続けるためには、
AIを“民主化”して、個人や中小組織が使えるようにするべきだ」
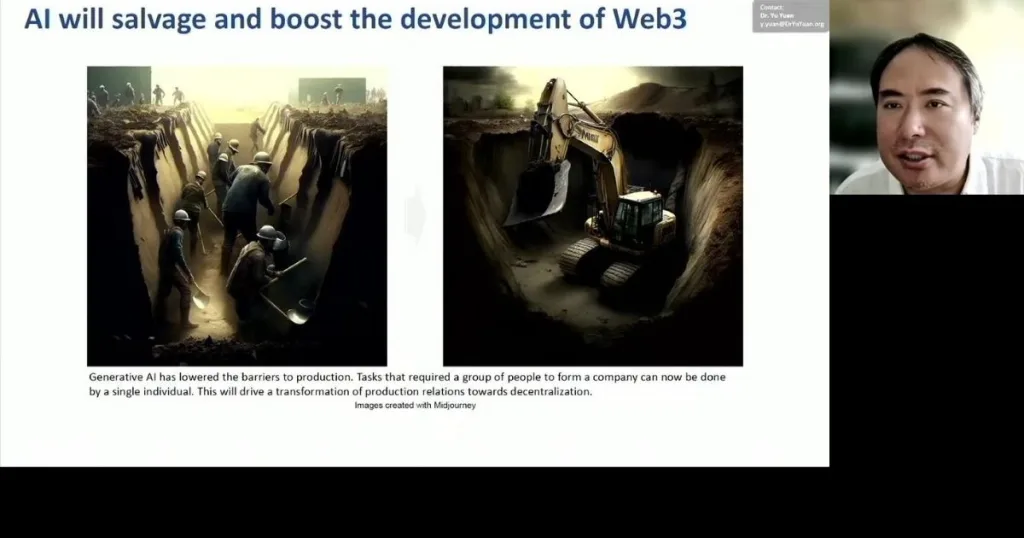
5. 未来のキーワードは「人間中心の共存」
Yu氏が提唱するのは、「Horizontal AGI(水平型の汎用AI)」という考え方です。
これは、AIの力を“上から与える”のではなく、
誰もが使いこなし、共に育てるような仕組みをつくるということ。
その先にあるのは──
- 世界中の人がAIを味方にして、新しい価値を生み出す
- 子どもがAIを活用して、自分の夢を形にする
- 小さな会社やチームが、世界とつながって挑戦できる未来
そしてYu氏は、こう結びました。
「私たちの使命は、人間とAIが共に成長し、共に繁栄する社会を築くこと」
「未来は、“共につくるもの”です」

6. おわりに:未来は、怖がるより“参加”するもの
AI、Web3、メタバース──
なんだか難しくて、自分には関係ないと思ってしまうかもしれません。
でも、Yu Yuan氏の言葉を借りれば、それは人間の未来そのものなんです。
怖がるのではなく、理解して、味方につける。
そして、私たちの“人間らしさ”を活かして、より豊かな世界をつくっていく。
それが、これからの「テクノロジーとの付き合い方」ではないでしょうか。

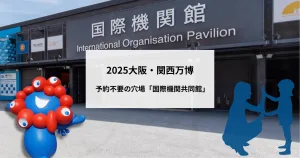

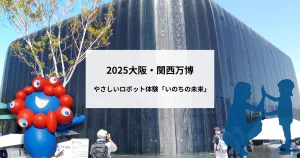
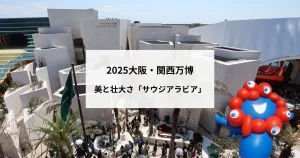
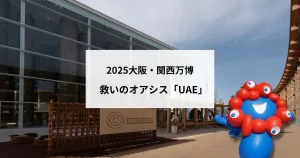

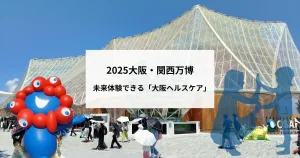
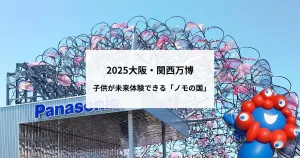
コメント